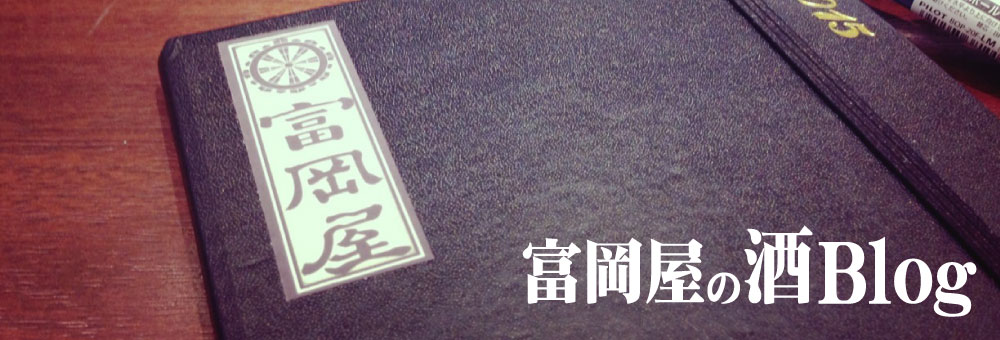
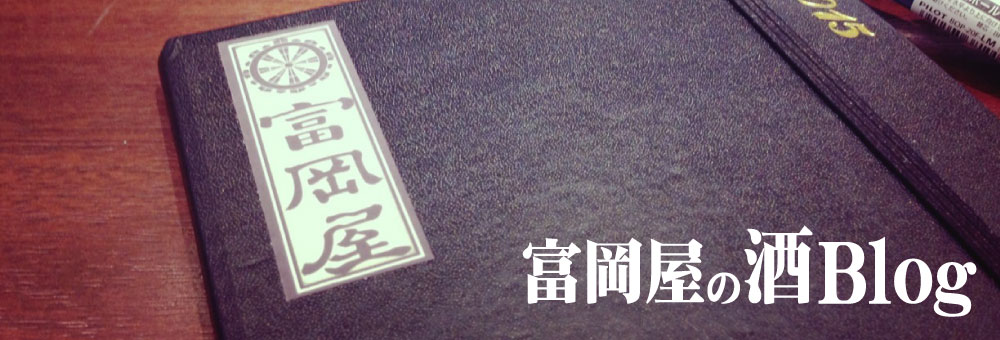
12.52014
次回アップするといいながら、ずいぶん間が空いてしまいました(*_*; いよいよ雪が降ってきましたねー(+o+)!
先日の「若鶴酒蔵見学」の続きです。 前回をチェックしていない方はコチラ★
前回は「大正蔵」の様子をお伝えしました。今回は「昭和蔵」の様子をお伝えします(^^)
さすがは大手の若鶴さん。蔵とはいえ、もはや工場…はたまた学校のような雰囲気です。
昭和蔵は、大変有難いことに、杜氏の籠瀬信幸さん自身が案内して下さいました!!
杜氏(とうじ)とは、簡単に言うと酒造りのチームのリーダーのことです!
普段こうして、商品を通して名前を目にしている方に、直接案内していただけるなんて本当に光栄でした。
ドキドキしながら昭和蔵に入ると、中は・・・そうあの香りです!私個人は「琳赤を開けたときの香りだ~(*’▽’)」と思いました。そのなんとも言えない甘いようないい香りが、蔵中に漂っているんです。見学者一同「いい香り~」とウットリしながら、すでに半分飲んだ気持ちになっていました(笑)
この様に機械化されている部分もありながら、やはりお酒造りは人の手があってこそ!
特に大吟醸などランクの高いお酒になると、とことん手造りにこだわって、丁寧に造られているという事がよくわかりました(>_<)
下のタンクに入っている白いものが酒母(しゅぼ)です。お酒の元になることから「もと」と呼ばれます。
こちらは仕込み部屋の様子です。下のようなタンクがズラリと並んでいました!
タンクの中にホースをつたって蒸米が入れられます。
こちらは「琳青」にも使われる、富山県産の雄山錦の蒸米です!
お酒造りは本当にデリケートなものの様で、同じ分量でそれぞれ酒母に麹・蒸米・水を加えても、ひとつとして同じになるものはないという事でした!(>_<) 籠瀬さんいわく、まるで人間のように「イライラしている酒」「機嫌のいい酒」がわかるそうです!発酵の様子が小さい泡をブツブツといくつも出しているとイライラ・・・大きな泡をポッコリとゆっくり出しているとご機嫌・・・というように…奥が深いです(>_<)
そうした酒の様子を見て、いい酒になるように導いてあげるのが、❝蔵人の仕事❞とおっしゃっていました。
そうして手間暇かけられたお酒が、私たちの元に届いているんだと思うと、今以上に愛着がわきますね。
温度変化に敏感なお酒は、人間が運動して汗をかくのと同じで、すぐに雑味が出てしまう為、今の季節のような厳しい寒さの中で仕込みが行われるということです。
最後に酒蔵のシンボル、杉玉の下で1枚。
真ん中が籠瀬さんです。
今回は本当にいい体験をさせていただきました!!
若鶴酒造さん、見学を企画して下さった荻原さん(お着物が素敵な利き酒師の方です!)、
本当にありがとうございました。
今年の五月に、若鶴さんの「蔵祭り」帰りのお客様が何人もお店に寄って下さったんですが、次回は私も参加したい!!!と強く思いました( `ー´)ノ
・・・皆さんお楽しみに♡
Copyright © 富岡屋 All rights reserved.